- If you turn to the left, you will find the library....①
「左に曲がれば図書館があるよ。」 - =Turning to the left, you will find the library....②
まずは「分詞構文」の確認だ。②が「分詞構文」とされるものである。「分詞構文とは分詞(=
turning)が接続詞(=if)・主語(=you)・動詞(=turn)の役割を兼ねる構文である」とされる。そしてifとyouを除去し、turnに-ingを付ければ「一丁あがり!」と教えられる。次は…-
As night came on, we went home....③
「日が暮れたので、家路についた」 - =Night coming on, we went home....④
こちらは
nightが消えずに残っている。前後で主語が違うので、省略したら何が主語だったか分からなくなるからだ。こちらは特に「独立分詞構文」と呼ばれる。さて今回のテーマは「分詞構文なんて何であるの?」だが、その前に巷(ちまた)で流布(るふ)する或る「トンデモ説」を論破する。「分詞構文・動名詞起源説」だ。
(In) doingは「~の時」で、「inが省略されて分詞構文ができあがったのだー!」と言うものだ。では他の接続詞は?だが(because of) doing「~なので」/ (in spite of) doing「~だけれども」/ (and resulted in) doing「そして~した」などで全て説明がつくと言う。だがこんなことは1万パーセントあり得ない。ラテン語にもギリシャ語にも、「分詞構文」も「独立分詞構文」も既に存在するからだ(流石にヘブライ語には無い)。用法も現代英語のそれと寸分違わない。分詞構文は「紀元前」から存在するのだ。独立分詞構文をラテン語では「絶対奪格(
Ablativus Absolutus)[アブラティーウス・アプソルートゥス]」と、ギリシャ語では「独立属格(Genitivus Absolutus)[ゲニティウス・アプソルートゥス]」と呼ぶ。前者は分詞構文の「意味上の主語」を「奪格(目的格の一種)」に、後者は「属格(所有格)」に置くことからこの名がある。つまり④の例文のnightは「主格」ではなく「目的格」なのだ。さらに例⑤⑥を挙げる。下線部前者がラテン語、後者がギリシャ語方式である(「動名詞」の用例で恐縮だが「動名詞は現在分詞の名詞的用法」故ご容赦願いたい)。ギリシャ語で「属格」を使うのは、ギリシャ語には「奪格」が存在せず、「属格」が「奪格」の機能を継承したからである。-
He is proud of his father / his father's being rich...⑤
「彼は父親が裕福なことに誇りを持っている」 -
Would you mind me / my opening the window?...⑥
「私、窓開けるけどいい?」
この説の提唱者(高校英語の先生らしい)はなぜ袋小路に迷い込んでしまったのか? どうも「現在分詞は動作が進行中であることを表す」と固く信じておられるらしい。「
Not knowingなどありえない(状態動詞ゆえ)」⇒「これは動名詞に違いない」となって、後はご自説に有利な材料だけを集められたようだ(絶対やってはいけないことである)。「be+~ing」は確かに「動作の進行中」を表すが「~ing単体」ではそんな縛りは無い。そもそも「動作」と「状態」を区別する言語は英語だけ。しかも近代英語に突発的に現れた現象である(「進行形はヘブライ語起源」参照)。日本語でも我々は「似ている(状態)」と「走っている(動作)」を区別していない。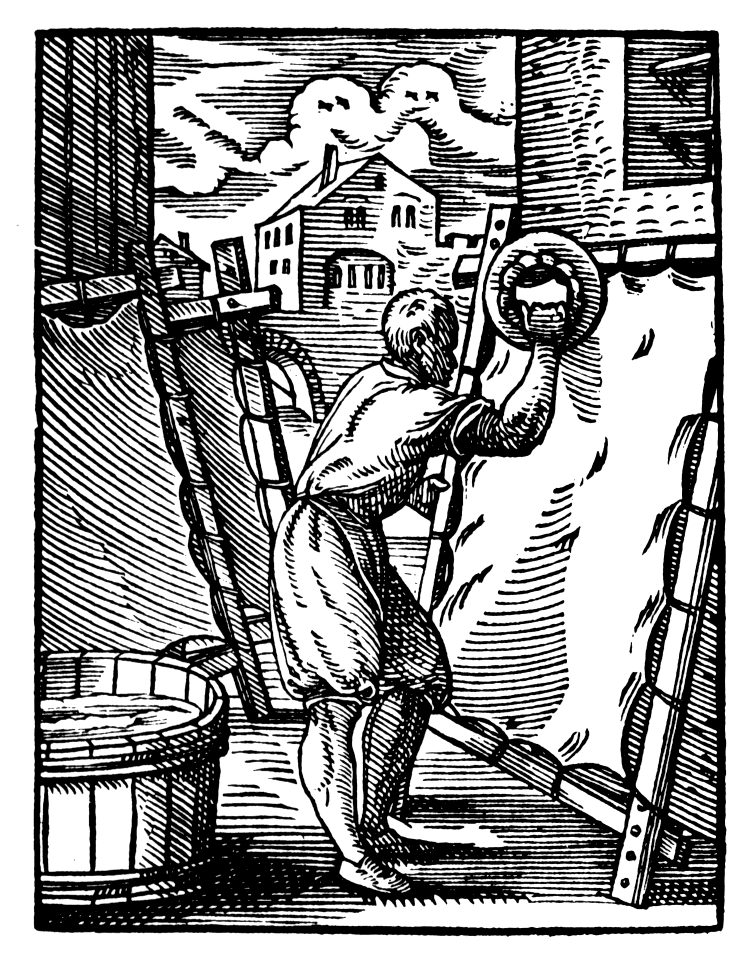 さらに別の方の説では分詞構文発達の要因として「当時は羊皮紙が貴重だったから文章を短くする為だったー!」と言う。「どひゃー!」と、思わずのけぞってしまった。近代英語の話と思いきや、いつのまにか「古代ローマ」に話が飛んでいるのだ。だがこの方はラテン語を恐らくはご存知ない。「分詞構文を使えば文が短くなる」というのは「英語しか知らない人」の発想だからだ。「主語が無くなれば文が短くなるはず」と考えたのだろうが、生憎ラテン語には(そして我らが日本語にも)「主語は(ほぼ)登場しない」。動詞の形を見れば主語が何かが分かるからだ。故に「主語」を英語で
さらに別の方の説では分詞構文発達の要因として「当時は羊皮紙が貴重だったから文章を短くする為だったー!」と言う。「どひゃー!」と、思わずのけぞってしまった。近代英語の話と思いきや、いつのまにか「古代ローマ」に話が飛んでいるのだ。だがこの方はラテン語を恐らくはご存知ない。「分詞構文を使えば文が短くなる」というのは「英語しか知らない人」の発想だからだ。「主語が無くなれば文が短くなるはず」と考えたのだろうが、生憎ラテン語には(そして我らが日本語にも)「主語は(ほぼ)登場しない」。動詞の形を見れば主語が何かが分かるからだ。故に「主語」を英語でsubject(sub + jacio:下に投げ入れられたる物⋯が原義)と言うのだ。従って分詞構文にしようがするまいが、長さは1ミリも変わらない。「接続詞」を省略しても、その分「分詞」に活用語尾が付く。いいとこ「トントン」である。確かにラテン語はコンパクトだ。しかしそれは何も分詞構文のせいではない。ラテン語には(繰り返すが)「主語」が無い。「冠詞」も無い。「前置詞」も(ほぼ)登場しない。必要とあらばbe動詞すらバッサリやる(名詞文)。そもそも分詞構文は1文に1度しか使えない。仮に2~3文字減らしても、何の足しにもならない。こんな説に労力を費やすのなら1つでいい。「英語以外の言語」を学んでみることだ。見える景色が全く違ってくるはずだ。では本題に入る。①と②を見て欲しい。分詞構文の作成手順としては上述した通りでいいのだが、これでは①から②ができたような印象を与えてしまう。①と②はまったく別の文なのだ。分詞構文は「文語的表現」である。「口語(話し言葉)」ではない「改まった格調高い文」ということだ。この「分詞構文を多用する言語」に古代ギリシャ語が挙げられる。それどころか「分詞構文の無い文など存在しない」とすら言える。イソップ寓話などには分詞構文が7つも連なった文が、ホメロスの「イリアス」と「オデッセイア」にはそれぞれ冒頭のセンテンスで早くも分詞構文が登場する。ラテン語との比較には「新約聖書」が適任だ。書かれた内容は同じでも、ギリシャ語は分詞構文を多用する。一方ラテン語には分詞構文が(皆無とは言わぬが)非常に少ない。「接続詞+S+V」という、所謂(いわゆる)「節(せつ)」を用いて律儀に細かく文を切る。
では分詞構文を用いると、一体どんなニュアンスになるのか。何故古代ギリシャ人は、偏執狂的なまでに分詞構文に拘泥(こうでい)したのか? 一時期筆者は「まだ接続詞が未発達だった為では?」と考えていた。どこかでそんな説を読んだからだ。そこで短い間ではあったが師事したギリシャ語の先生にこの疑問をぶつけてみた。すると「そんなことはないよ鈴木くん。ギリシャ語は英語なんかより、遥かに接続詞の数は多いんだ」との答であった(後年筆者はこの師の言葉を思い知らされることとなる)。
ではどうしてギリシャ人は分詞構文を好んだのか? それは「リズム」であるという。古代ギリシャ人は「学問・芸術」をこよなく愛した。文章自体も単に情報伝達の手段としただけでは事足れりとせず、それを美しく相手に伝えることに拘(こだわ)ったのだ。読んで、聞いて、美しいと感じるためには文の切れ目は少ない方がいい。英語でもそれは変わらない。手元の英文を声に出して読んでみて欲しい。接続詞が登場すれば必ずリズムが寸断される。折角いい気分で読んでいたのに、不愉快な事この上ない。こういった無粋な文章を、ギリシャ人は何より嫌ったのだ⋯と。
更に「知的遊戯」としての側面も見逃せない。接続詞が明示されないから文の前後関係から繋がりを類推するしかなく、読む側は「謎解き」を要求される。しかしその「サスペンス感」が読む者を引き込む。一種の「推理小説」だ。最初から犯人が分かっている小説など誰も読まない。音で楽しみ文字で味わう。故に「文語」なのだ。古来和歌や短歌、俳句を愛(め)でてきた日本人なら分かるはずである。
一方古代ローマ人は実利的民族であった。古代ローマが後世に残したものは「土木(ローマ道)」と「法律(ローマ法)」である。いわば「大手ゼネコン」と「悪徳弁護士」を兼務したようなものだ。学問・芸術はからっきしダメなのだ。無論彼らが古代ギリシャ文明に憧憬(しょうけい)の念抱くこと、生半可なものではなかった。故にその黎明期には多数の留学生をギリシャに送り、その文化の摂取に努めた。地中海版「遣唐使」である。しかも日本のそれより1000年も古い。しかし「豹はその斑点を変えられない(旧約聖書・エレミア書・13-23)」。民族にはそれぞれ生まれ持った適性がある。古代ローマが古代ギリシャに追いつくことは遂になかった。上述したギリシャ語の先生は古代ローマ人をして「古代ギリシャに憧れて、憧れて、憧れぬいて、そして遂に力尽きた民族」と評した。まこと慧眼(けいがん)であろう。
最後に「分詞構文の
beingはしばしば省略」されるが、これはラテン語の影響である。ラテン語にはbeingに相当する単語が無いからだ。のみならず、分詞の種類は非常に「貧困」である。1つの動詞からギリシャ語は396個(by筆者カウント)もの分詞が誘導される。対するラテン語は僅か100個(英語は無論2個)。分詞構文を作ろうにも「無い袖は振れない⋯」という「お家の事情」もあったようだ。尤(もっと)もこの事実をもって「ラテン語の方が引き締まった感触を与え、それが魅力となっている」と評価する方もいる。There is no accounting for tastes「蓼(たで)食う虫も好き好き」である。
